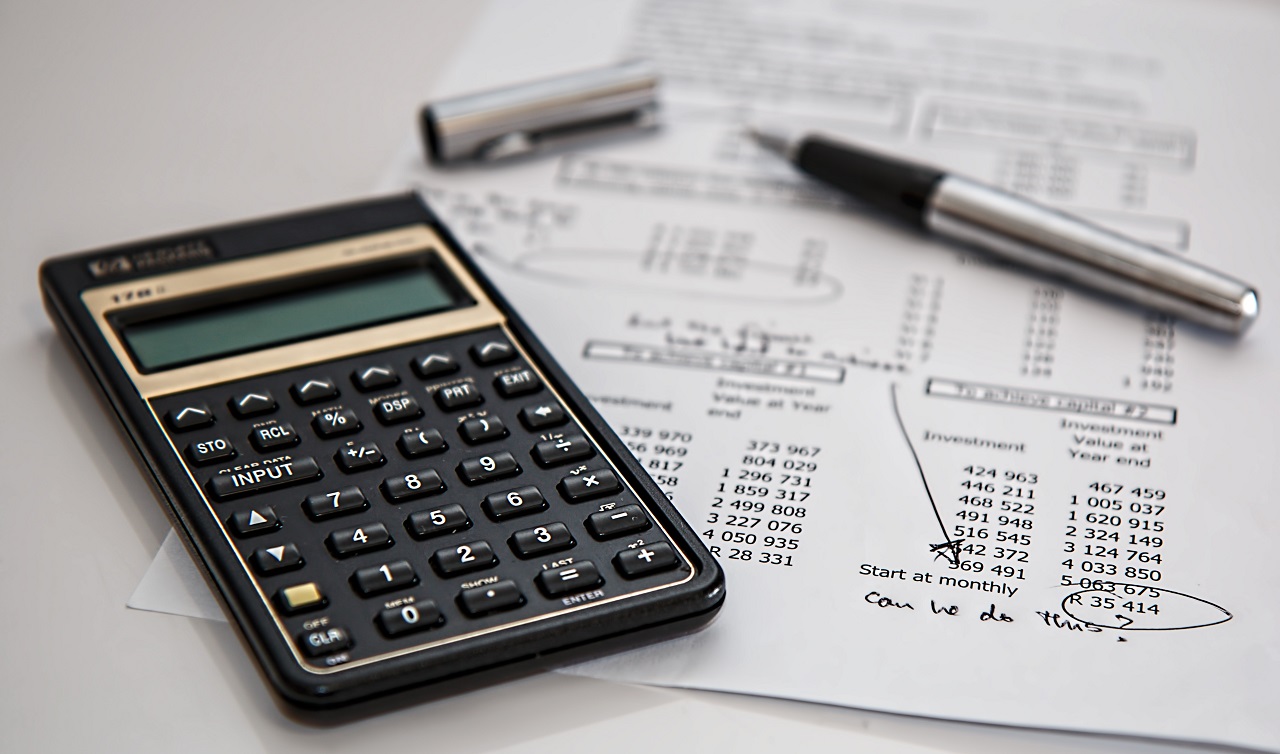1 はじめに
裁判所を通じた比較的活用しやすい債権回収の方法に「支払督促」というものがあります。本記事では、支払督促の概要や手続きの流れ、注意点、支払督促の活用に適した場面などについてお伝えします。
2 支払督促とは?
支払督促は、簡易裁判所から債務者に対して金銭の支払いを命じる文書を送ってもらう手続です。
支払督促は、まずは簡易裁判所に支払督促を申立て、支払督促を債務者に送ってもらいます。その後、債務者から異議が出なければ、簡易裁判所に仮執行宣言の申立てをし、仮執行宣言の付いた支払督促を債務者に送ってもらうという2段階の手続になっています。
支払督促は、証拠を提出せず簡単な書面審理のみで進行するため、迅速かつ簡易に利用できます。さらに、簡易裁判所から仮執行宣言の付いた支払督促を債務者に送ってもらうことができれば、債務者の財産に強制執行ができるようになるという強い効力を持ちます。支払督促には、訴訟と比べて裁判所に納める手数料が半分で済むというメリットもあります。
支払督促は簡易裁判所を通じた手続ですが、請求金額に140万円以下といった制限は設けられていません。
このように、メリットが大きいように感じられる支払督促ですが、もちろん注意すべき点があり、活用に適さない場面もあります。
3 支払督促の手続きの流れ
ア 支払督促の申立て(1段階目)
簡易裁判所の裁判所書記官に支払督促の申立書や添付書類を提出します。この際、手数料分の収入印紙や裁判所から指示された金額の郵便切手も提出します。
申立書の提出先は、債務者の住所等を管轄する簡易裁判所です。
裁判所書記官が申立書等の書類を審査し、問題がなければ、債務者に支払督促を発付します。
イ 債務者の異議申立の機会
支払督促が債務者に送達されると支払督促の効力が生じますが、債務者は支払督促に対して異議を申し立てることができます。支払督促への異議の申立ては、仮執行宣言がされる時まで行うことができます。
異議が申立てられた場合、支払督促はその異議の限度で効力を失うとともに、通常の訴訟に移行します。つまり、債務者との間で訴訟をすることになってしまいます。
ウ 仮執行宣言の申立て(2段階目)
支払督促が債務者に送達されてから2週間以内に債務者から異議の申立てがない場合は、仮執行宣言の申立てを行うことができます。支払督促の申立てに続く、2段階目の手続です。
支払督促が債務者に送達されてから2週間を経過した日の翌日から30日以内に仮執行宣言の申立てをしない場合は、支払督促が失効するため注意が必要です。
裁判所書記官から支払督促に仮執行宣言を付けてもらい、これが債務者に送達されれば、債務者の財産に強制執行ができるようになります。
エ 債務者の異議申立の機会
上記イの異議申立とは別に、債務者は仮執行宣言付支払督促に対しても異議を申立てることができます。仮執行宣言付支払督促への異議申立ては、債務者に仮執行宣言付支払督促が送達されてから2週間以内であれば行うことができ、これを過ぎると異議申立はできなくなります。
債務者からの異議申立がされた場合、通常の訴訟に移行します。なお、仮執行宣言付支払督促に対する異議の場合は、仮執行宣言付支払督促は効力を失わないため、債務者が強制執行を避けようとする場合は、強制執行の停止又は取消しの申立てを行う必要があります。
4 支払督促を活用する際の注意点
ア 対象は金銭等の給付請求
支払督促の対象は、金銭(その個性が問題とならない有価証券等を含む)の給付請求に限定されています。
例えば、債務者にお金の支払を請求する場合は支払督促が利用できますが、賃貸物件の明渡しを求めるときなどは支払督促を利用できません。
イ すぐに執行できない請求は非対象
請求の期限がまだ来ていない請求権や、請求のための条件が付いている請求権は対象となりません。
ウ 債務者が所在不明の場合は利用不可
支払督促は、債務者に国内送達(公示送達を除きます)できる場合でなければ利用できません。債務者の所在が分からない場合は利用できないことになります。
エ 異議申し立てによる訴訟への移行
債務者が異議を申し立てた場合、訴訟に移行します。したがって、訴訟移行のリスクを知ったうえで、申立てを行う必要があります。
オ 仮執行宣言の申立てを失念しない
支払督促が債務者に送達されてから2週間を経過した日の翌日から30日以内に仮執行宣言の申立てをしない場合は、支払督促が失効するため注意が必要です。
仮執行宣言の申立てを期間内に忘れず行う必要があります。
5 支払督促の活用に適した場面
支払督促の活用に適していると考えられる場面について記載したいと思います。
ア 債務者が債務の内容を争わないことが予想される場合
債務者が債務の内容を認めている、契約書などの明確な証拠があるなど、債務者が債務の内容を争わないと予想される場合は、支払督促の活用が選択肢に入ってきます。
例えば、債務者が支払の義務があることは争っていないが、支払時期を先延ばしにして支払おうとしない、支払に向けた具体的な話をしようとしない、途中で連絡が取れなくなったという場合が考えられます。
イ 裁判所を通じた迅速な解決を試みたい場合
支払督促は通常の訴訟よりも早期に進めることができるため、裁判所を通じた迅速な解決を試みたい場合は、支払督促の活用が選択肢に入ってきます。
ただし、債務者から異議を出されて訴訟に移行し、訴訟で争うことになると、迅速な解決が見込めなくなることには注意が必要です。
ウ 債務者の管轄地で訴訟をしてもよい場合
支払督促は、債務者の住所等を管轄する簡易裁判所で手続を進めることになりますが、債務者から異議が申立てられ、訴訟に移行すると、請求額が140万円以下であればその簡易裁判所、請求額が140万円を超えるとその簡易裁判所を管轄する地方裁判所で審理が行われます。
つまり、異議が申し立てられると、債務者の住所等を管轄する裁判所で訴訟をすることになります。
この点を気にする必要がない場合は、支払督促の活用を検討することができます。
6 支払督促を活用すべきでない場合
支払督促が適さないと考えられる場面について記載したいと思います。
ア 債務者が債務の内容を争う可能性が高い場合
債務に関する明確な証拠がなく、債務者が債務の内容を争っている場合は、債務者から異議申し立てが行われる可能性が高いといえます。
このような場合は、支払督促ではなく、主張や立証の方法を十分に組み立てたうえで、訴訟の提起などを検討することになります。
イ 債務者の管轄で訴訟に移行すると困る場合
支払督促に異議が申し立てられると、債務者の住所等を管轄する裁判所で訴訟をすることになります。
債務者が異議申立をする可能性があって、債務者の住所等が遠方であり、そこで訴訟対応するのは困るという場合は、支払督促は適さないと思われます。
ウ 債務者が所在不明の場合
債務者の所在が分からない場合は支払督促を利用できないためです。
エ 債務者が財産をもっておらず、支払う意思も全くみられない場合
これは支払督促というよりは、債権回収全般に当てはまることです。
債務者が財産を持っておらず、支払う意思も全くみられない場合は、そもそも回収自体が困難です。
債務者が支払をしない場合、最終的には、債務者の財産に対する強制執行によって債権回収を図ることができます。しかし、債務者が財産を持っていない場合は、そもそも強制執行の対象が存在しません。そのような債務者が強制執行を恐れる可能性は低いと思われます。
財産がなくとも、支払の意思がある債務者であれば、分割で少額ずつでも回収ができるかもしれません。支払の約束の文書を作成したり、連帯保証人を立ててもらうことも考えられます。
しかし、財産がないうえに、支払の意思が全くみられない債務者の場合、支払督促などの法的措置をとったところで、1円も回収できずに、法的措置のための費用や労力がかかってしまったということになりかねません。
このような事態を予防するためには、取引時の与信管理が最も重要と思われます。
7 さいごに
支払督促は、債権回収の有効な手段の一つです。支払督促の概要を知っていただければ、今後のいざという時に役立てられるのではないかと思います。
ただし、債権の内容、証拠の内容、交渉の経緯、債務者の言い分や態度、債務者の管轄地、債務者の財産状況などから、支払督促の活用が適切かどうかは慎重に検討していただけますと幸いです。